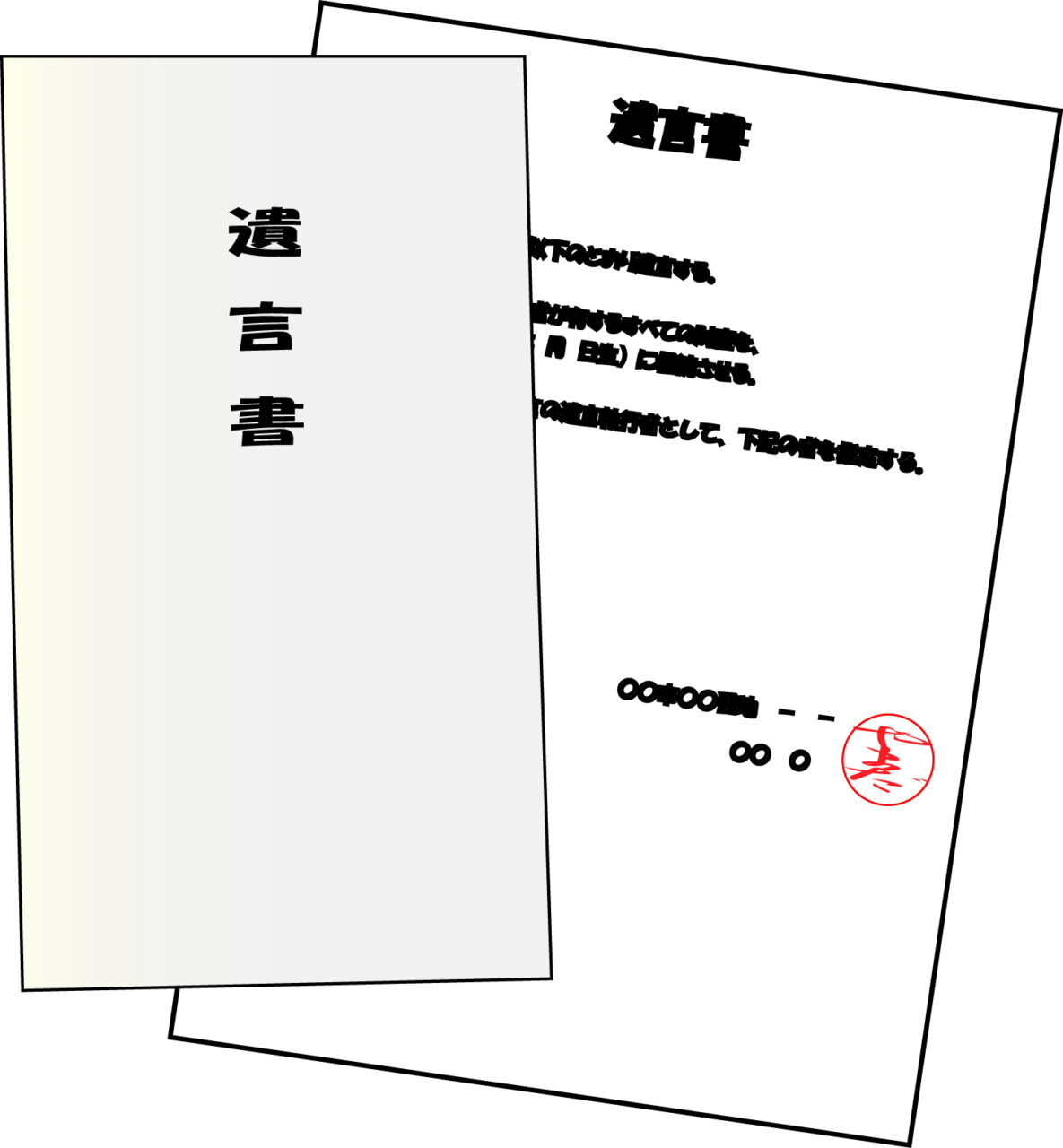こんにちは、芦屋のうちで法務事務所 代表司法書士の向井亜希子です。
「いごん」なのか「ゆいごん」なのか…そんなことを依頼者様に聞かれることがありますが、どちらでも構いません。一応、法律用語としては「いごん」ですが、一般的には「ゆいごん」と言われることが多いですよね。
この度、近隣の司法書士と共同で遺言のことをまとめた冊子を作成いたしました。
遺言のことだけでなく、相続が起きたときにするべきチェックリスト等もまとめてありますので、必要な方はご連絡いただければお渡しいたします。(事務所の前にも置いてありますので、お気軽に取ってください。)
冊子に書いたことの抜粋にはなりますが、今回は遺言についてご説明します。
遺言の種類
さて、遺言にはどのような種類があるかご存知でしょうか。
メジャーなのは
・公正証書遺言
・自筆証書遺言
ですが、他に秘密証書遺言というものがあります。この3つを、普通方式の遺言といいます。
秘密証書遺言とは
遺言書の内容を秘密に作成し、その遺言の存在を公証役場にて確認してもらう遺言です。 公正証書遺言同様、公証役場にて手続きをしますが、その手続き内容は遺言書の存在確認のみで、記載内容や法律に沿って書かれているかなどは確認しません。誰にも内容を知られたくない方におすすめですが、中身の確認を誰もしないため、実は無効だった…ということも起こりえます。
他にも、さらにマイナーな存在ですが、特別方式の遺言といって、特殊な状況下でのみ利用される遺言の形式ですがあります。
めったにお目にかかることはありませんが(わたしも見たことがないですし、先日、司法書士歴40年近いベテランの先生が「初めて見た!」と言っていたくらい、レアな存在です)せっかくなので簡単に紹介しますね。
| 状況 | 要件 |
|---|---|
| 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をするとき | ・証人3人以上の立会い ・証人の一人に遺言の趣旨を伝える ・その証人がこれを筆記して,遺言者及び他の証人に読み聞かせる又は閲覧させる ・証人全員が筆記の正確なことを承認した後、これに署名し印を押す ・遺言の日から20日以内に証人か利害関係者によって確認を得る |
| 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にいる者 | 警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作る |
| 船舶に乗船している者 | 船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作る |
| 船舶が遭難した結果死亡の危急に瀕した場合 | 証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる |
ここからは、メジャーなふたつについて少し詳しくご紹介します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、本人が全文を自筆で書いて作成する遺言書のことです。
公証役場に行く必要もなく、費用もかからないため、もっとも手軽な遺言の方法として知られています。
- 遺言者が全文を自筆(パソコン・代筆は不可)
- 日付を明記(〇年〇月〇日まで明記)
- 氏名を署名し、押印(認印でも可)
- 財産目録はパソコン作成やコピーでもOK(ただし各ページに署名押印が必要)
メリット
- 費用がかからない
紙とペンさえあれば作成でき、弁護士や公証人に依頼する必要がありません。 - 誰にも知られず作成できる
秘密裏に自分の意思を記しておけます。 - 自由度が高い
伝えたいことを自分の言葉で書くことができます。
デメリットと注意点
- 形式不備で無効になる恐れ
法律上の要件を満たさないと、せっかく書いても無効になることがあります。 - 紛失や改ざんのリスク
家に保管していると、第三者に隠されたり、破棄される可能性も。 - 死後、家庭裁判所の検認が必要
相続人が遺言書を発見した場合、開封前に裁判所で「検認」の手続きをしなければなりません。
自筆遺言を法務局で保管する制度もあります。
法務局が、自筆証書遺言を安全に預かってくれる制度です。
2020年7月10日からスタートし、手軽に・確実に・安心して遺言を残すことができるようになりました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
✅ 裁判所の検認が不要!
通常、自筆証書遺言は死後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要ですが、
この保管制度を使った遺言書なら、そのまま相続手続きに使えます。
✅ 紛失・改ざん・隠ぺいの心配なし
法務局(法務省)が厳重に保管するため、自宅保管に比べて安心感が段違いです。
費用は一通3900円とリーズナブルです。
自筆証書遺言をお考えの方は、ぜひ上のリンクから説明を読んでみてください。
遺言書自体の作成は司法書士などの専門家にサポートを依頼して、法務局で保管してもらうのもお勧めです。
公正証書遺言
公証役場で、遺言者の意思を確認しながら、公証人が公正証書の形で作成する遺言です。
原本は公証役場に保管されるため、改ざん・紛失の心配もありません。
メリット
- 法的に最も確実な遺言方式
専門家が作成するため、形式不備で無効になるリスクがほぼゼロ。 - 原本が公証役場に保管される
遺言書の破棄や改ざん、紛失の心配がありません。 - 家庭裁判所の「検認」が不要
死後すぐに内容を実行可能。相続手続きもスムーズです。 - 本人の意思能力を証明しやすい
高齢者でも、認知症でなければ公証人が判断し、証人とともに記録するため、のちのトラブル回避に役立ちます。
デメリット
- 費用がかかる(作成手数料は財産額により異なります)
- 証人2人が必要(司法書士等の専門家に依頼可能です)
作成の流れ
- 事前準備(財産目録、家族構成、意向の整理)
- 公証役場に相談・日程調整
- 証人2名を用意
- 遺言内容を口述 → 公証人が文章化
- 署名・押印して完成
※必要な書類を集めたり、考えをまとめたり、公証人と打合せを行うことにつき、法律的な知識が必要になる場合があります。司法書士などの専門にまず相談し、段取りを整えることも可能です。
費用の目安
作成費用は財産額や内容により異なりますが、たとえば:
- 遺産総額1,000万円 → 約2~3万円前後
- 遺産総額5,000万円 → 約5~7万円前後
証人を依頼する場合や、出張をお願いする場合は別途費用がかかります。
また、司法書士などの専門家にサポートを依頼する場合は別途費用が必要です。
公正証書遺言は、費用はかかるものの、信頼性・安全性・確実性の点で最も安心できる遺言方法です。特に、以下のような方におすすめです:
- 高齢で自筆が難しい方
- 相続人同士のトラブルを避けたい方
- 不動産や預貯金など多くの財産を持っている方
遺言は、あなたの大切な想いと財産を、確実に家族へ届ける手段です。トラブル防止のためにも、今こそ準備を始めましょう。